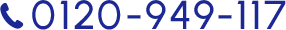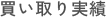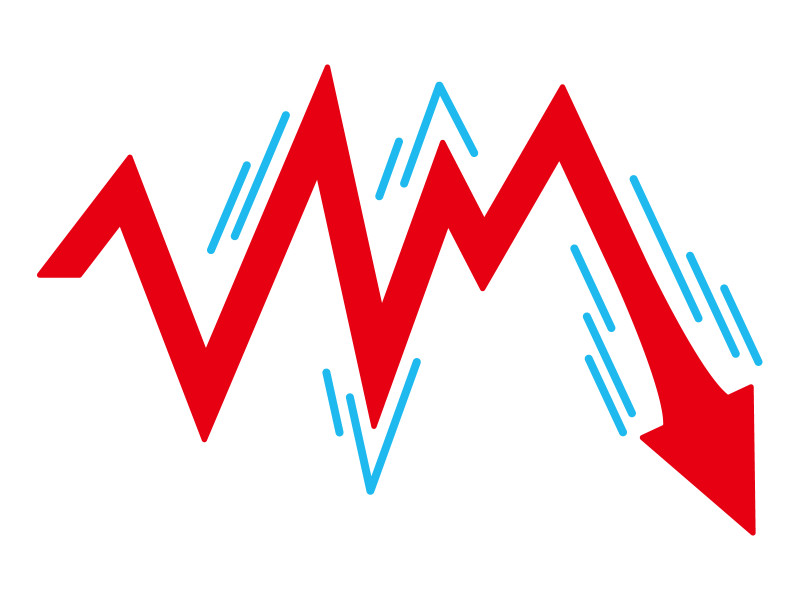特約事項について

宅建業者の業務の中に、売主、買主の意向を確認しながら、契約書を作成することが含まれています。
しかし、契約書を白紙からひとつひとつの条文で毎回作ると、とても大変な作業で時間も相当かかってしまいます。
よって、事前に標準的な書式を用意して、個々の契約書を作成していきます。
通常は、民法に定めのない事項に関する約定、あるいは、民法の規定と異なる約定(民法に対する特約)を含めて、不動産取引を正常に行う条項が盛り込まれています。
一般的な取引であれば、標準書式をそのまま使用して売買契約を締結することが可能です。
しかし、必ずしもこの範囲でやらなければならないということはありません。
売主と買主の当事者間の合意により、個別に条件を設定することはよくあります。
例えば、特約事項の一つに、売り手が住み替えで引き渡し猶予期間を設ける場合があります。
代金決済を受けてから引越しを手配するため、決済後もある一定期間の滞在を買い手に認めてもらうことを条件に契約を交わします。
また、売主自身は引き渡し時に清掃はしない代わりに、専門業者によるハウスクリーニング行ったりします。
これについても特約に盛り込み、引き渡しの条件としておくことが必要になります。
特約条項には、いかなる条文も盛り込むことは原則可能です。
しかし、「公序良俗」や「強行法規」に違反するものは、その効力が認められません。
公序良俗とは、「社会的妥当性」のことを言いますが、とても曖昧な内容です。
この内容決定については、裁判所の判断に任されています。
例としては、買い手が買った後に夫婦で同居することは認めないとする特約やばくち場として借家契約を結ぶことを条件にしたものがあります。
これらは、一般常識や道徳上においてもおかしな条件にあたるので、認められないとされています。
強行法規とは、法令中の規定のうち、当事者間の合意に関わらず適用されるものをいいます。
例えば、民法では瑕疵担保責任については瑕疵を知った時から1年以内のものに制限しております。
その規定の範囲を超えて、期間を設定しているものは、強行法規が適用されて、1年以上の設定した期間については効力が認められないことになります。
購入申込みを受けた時から、交渉の段階に至るまでの経緯の中で交渉してきたことを特約事項に記載して、契約書に反映させることになります。
契約書にサインする前に、交渉内容がしっかりと盛り込まれているかどうか、公序良俗、強行法規に違反しているものがないかなどを、担当者と一緒に確認しておくようにしましょう。
北海道札幌市白石区北郷4条4-1-1
0120-966-972 / 011-376-5786
営業時間:9:00~20:00
定休日: 水曜日